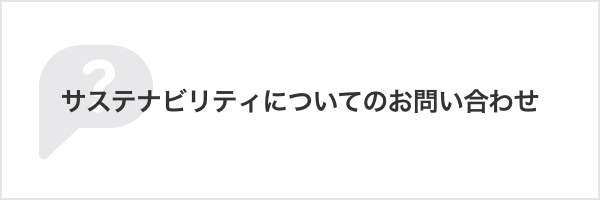資金運用を通じたSDGs、社会貢献、環境問題などへの取り組みを行っている芦屋市と、2017年度以降グリーンボンド、2019年度からはサステナビリティボンドを継続的に発行している独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構によって、SDGs債市場の更なる発展を目指したエンゲージメント対談が行われました。

近年、ESGに関する意識の高まりとともに、債券市場におけるESG 債の割合が急速に高まっています。ESG債は、ソーシャルボンドであれば社会的課題の解決に、グリーンボンドであれば環境課題の解決に、サステナビリティボンドであればその双方に繋がるため、投資家の立場から見ると、償還が予定された上で利回りを得られる債券としての商品性に、これらの課題解決への貢献という動機が加わることになります。
SDGs債の市場拡大に伴い、投資家と発行体によるエンゲージメントの重要性が高まっています。対談を通じて投資家・発行体の両者がお互いの事業やファイナンス・運用、SDGsへの取り組みについての理解を深めることで、両者のSDGs等に関する共通点を探り、サステナブルな関係を築いていくことにつながります。独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(鉄道・運輸機構)が発行するサステナビリティボンドを芦屋市が昨年購入し、芦屋市より投資表明がなされました。

- 拡大
- 市の文化財として指定されている芦屋川にかかる公光橋にて
2024年6月25日、芦屋市役所において、芦屋市の髙島崚輔市長と鉄道・運輸機構の米田純一理事の対談が行われ、芦屋市、鉄道・運輸機構のSDGsに関する取り組みについて意見交換が行われました。

- 拡大
- 対談の様子
参加者
|
芦屋市 |
独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
野村證券株式会社 |
|
|
|
濟木:
本日はエンゲージメント対談ということで、投資家である芦屋市の髙島市長と債券のご発行体である鉄道・運輸機構の米田理事との対談を行わせていただきます。鉄道・運輸機構様と芦屋市様は、ESG投資において非常に密接なつながりを有しています。ESG/SDGsというテーマでどのような取り組みを行っているのか、また、サステナビリティボンドの発行に至った背景についてもお伺いしたいと思います。まず、芦屋市様のお取り組みや概況についてお話しいただけますでしょうか。
髙島氏:
芦屋市は自然を大事にしている住宅都市で、大きな会社や工場がほとんどありません。計画上、新しく工場を建設できないという厳しい規制をかけているなど、住む場所としての都市となっています。その中で大事にしていることは、いかに環境に配慮して自然と共に暮らせる街にしていくかということです。

- 拡大
- 芦屋市 髙島市長
芦屋川は、川全体が市の文化財として指定されています。芦屋川を上流に行くと六甲山の国立公園があり、公園の中にも実は奥池という住むエリアがあります。国立公園の中から海沿いまで、自然と調和できる住環境がここまで守られているのは、ひとえに市民のみなさまの力だと思います。例えば市内にはさまざまな街路樹がありますが、花や葉が散った後なども道がきれいなのは、住民の方々が朝早くから家の前を掃除されているからです。また、芦屋市は屋上などに大きな看板がありませんが、それは条例施行のタイミングで市民のみなさまが一斉に看板を下ろそうと協力してくださったからです。市民みんなで良い街並みを作ろうという姿勢が芦屋市の一番の強みです。
濟木:
その雰囲気というのは以前からなのでしょうか。
髙島氏:
以前からあると思います。芦屋市は日本で唯一の「国際文化住宅都市」です。芦屋国際文化住宅都市建設法という法律があり、内閣総理大臣は年1回芦屋市の街づくりについて国会に報告する義務があります。その法律がつくられたのは、実は住民投票の結果、賛成が多数だったからです。芦屋市は住宅都市として推進していくべきだという意見が多かったのです。元々そういう文化が根付いているのは、歴史を紐解いてもひとえに市民力だと思っています。
|
芦屋市略年表 |
|
|
昭和15年11月10日 |
市制施行 |
|
昭和26年3月3日法律第8号 |
芦屋国際文化住宅都市建設法 |
|
昭和35年8月1日 |
市旗制定 |
|
昭和37年3月31日 |
安全都市宣言 |
|
昭和39年5月3日 |
芦屋市民憲章 |
|
昭和42年11月3日 |
市民文化賞制定 |
|
昭和45年11月10日 |
市木「クロマツ」選定 |
|
昭和45年11月10日 |
市花「コバノミツバツツジ」選定 |
|
昭和56年4月1日 |
名誉市民条例制定 |
|
昭和60年10月15日決議 |
非核平和都市宣言(芦屋市議会決議) |
|
平成7年7月 |
芦屋市震災復興計画策定 |
|
平成13年3月 |
第3次芦屋市総合計画策定 |
|
平成16年1月1日 |
芦屋庭園都市宣言 |
|
平成23年3月 |
第4次芦屋市総合計画策定 |
|
平成28年3月 |
芦屋市創生総合戦略策定 |
|
令和3年9月 |
第5次芦屋市総合計画・第2期芦屋市創生総合戦略策定 |
濟木:
ありがとうございます。駅に降り立ったときに雰囲気が良いと感じましたが、その背景が非常によくわかりました。続きまして、鉄道・運輸機構様のお取り組みや事業などについてもお話しいただけますでしょうか。

- 拡大
- 鉄道・運輸機構 米田理事
米田氏:
鉄道・運輸機構は国が100%出資している独立行政法人ですが、主に鉄道の建設と船舶の建造の2つの事業を行っています。日本鉄道建設公団、船舶整備公団などが母体となっており、交通ネットワークをつくるという機関になっています。
主に行っているのは新幹線の建設です。国の計画に基づく整備主体として、最近では九州新幹線と北陸新幹線の2つの建設を手掛けました。九州新幹線については一昨年に武雄温泉・長崎間が、北陸新幹線については今年の3月に金沢・敦賀間が開業しました。現在は九州新幹線と北陸新幹線のプロジェクトがいったん終了したため、北海道新幹線の新函館北斗・札幌間の建設に注力している状況です。山の下を通しているため、8割がトンネルとなっています。

- 拡大
- 鉄道・運輸機構の系譜

- 拡大
- 整備新幹線について
北陸新幹線は敦賀・新大阪間、九州新幹線は新鳥栖・武雄温泉間の計画が未完成で、着工できていない状況ですが、敦賀・新大阪間については先行して地質調査を行っています。
北陸新幹線の開業イベントにも参加しましたが、地域のみなさまからも早く関西と繋がってほしいとの声を沢山いただきましたので、可能な限り早期の実現が図れればと思っています。鉄道による移動時間の短縮により、行先での滞在時間が長くなり、人との交流が深まる効果は大きいと考えています。インバウンドの方からも新幹線に乗ること自体が楽しいという声を聞き、改めて社会的な側面の強い事業であると実感しています。


新幹線の開業効果
当機構では、新幹線だけでなく、都市鉄道の建設も行っており、地域鉄道は昔の鉄建公団時代から全国各地でも行っています。兵庫県内でも過去には福知山線や智頭急行などを手掛けています。船舶については、環境負荷が低い船舶の建造や離島航路を維持する船舶など、政策的な意義があるものについて、共有建造という枠組みで、海運事業者へファイナンスや技術面でのアドバイスなどを提供しており、当機構は日本有数の船主となっています。
鉄道と船舶はいずれも環境にやさしい交通機関ということで、自動車と比較すると、輸送量当たりのCO2排出量はそれぞれ約1/6、約1/5になります 。

- 拡大
- 輸送量当たりのCO2排出量(2022年度)
出典:国土交通省総合政策局環境政策課HPより作成
髙島氏:
先日北陸新幹線に乗り、小松駅に行きました。素敵な駅のデザインでしたが、内装も手掛けられているのでしょうか。
米田氏:
はい。駅の建設に当たっては駅ごとにデザインを提示して市民の方に選んでいただいています。デザインについては地域の特色を踏まえて創っており、建材なども地域のものを活用しています。
高速道路のICと比較して語られることもありますが、新幹線の駅は、比べられないほど爆発的な経済効果があります。周辺の街づくりの効果にも影響するので、駅の魅力はとても重要で、先ほど芦屋市様のお話に、市民みんなでよい街並みを作ろうというお話がありましたが、駅が人の交流の場になることや、乗換えの時などにも気持ち良い空間であることが大事だと思っています。今進んでいる北海道新幹線の駅についても、デザインを地域の方に決めていただいています。
濟木:
芦屋市様も鉄道・運輸機構様もそうですが、地域のお声を大切にして巻き込んでいらっしゃるという共通点があると感じました。髙島市長は市長就任から1周年ということで、これまで注力されていることがありましたらお話しください。
髙島氏:
ひたすら言い続けていますが教育です。公立の学校教育を良くすることが街の未来を切り拓くからです。芦屋市の未来、そして日本全体の未来にとっても教育が一番大事だと考えています。
芦屋市では「ちょうどの学び」を掲げて、さまざまな取り組みを進めています。一人ひとりの個性・特性や興味関心、理解度は異なります。そんな中で、あらゆる人にとってちょうどよい学び方ができるような環境をつくっていきたい、一人ひとりに合った学び方を各人が選べるような環境にしたいと考えています。仕事でも同じですが、学校を卒業すると自分で自分に合った学び方を選ぶ場面が増えます。まずは自分に合った学び方・理解の仕方を知ってほしいと思っています。
教育分野において最大の課題は、子どもたちがなぜこの授業を学んでいるのかを理解できていないこと、ときには先生も分かっていないこともあるということだと考えています。良い学校に入って良い会社に入れば一生安泰という時代ではありません。自分が興味関心を持っていることが目の前の科目とどう繋がっているのかを知って、理解できた上で学びができると学びへのモチベーションが増すのではないかと思っています 。

- 拡大
- 芦屋市教育大綱
濟木:
予算面など障壁もあるようにも思えますが、いかがでしょうか。
髙島氏:
10年前でしたら無理だったと思いますが、今ならできると思います。それは大きな変化が2つあるからです。
1つは学校の先生が忙しすぎるということが可視化されてきたことにあります。働き方改革をしようという動きが出て、先生でなくてもできることを先生の手から切り離しやすくなっています。部活動の地域への移行がわかりやすい例だと思います。
もう1つは生成AI等の活用しやすい技術の台頭です。社会の風潮と技術が相まって、活用しやすい土壌ができてきていると感じています。芦屋市は、「教育のまち」を標榜してきました。教育委員会に任せっきりではなく、市みんなでサポートしていく体制を作り、市民の皆さまも巻き込み、「最高の教育ができる芦屋」を実現したいです。
濟木:
素晴らしいですね。当社も金融経済教育を小学校から社会人に至るまで90年代から行っています。「街のTシャツ屋さん」という、子供たちがTシャツ屋さんを起業して株式会社を作るというテキストを作っています。また、社員が全国の小中学校で出張授業を行っています。当社以外でも色々な会社が出張授業を行っているという話を聞き、先生のサポートという意味においてもそうですが、社会に出て役に立つことをいつもの授業とは別に受けられるのは理に適っていると感じました。
髙島氏:
特別授業が入ってくることによって、先生の負担が小さくなるというのは確かにあるかもしれませんが、同時に気をつけなければならないと思うのが、特別授業は社会とつながり、普段の授業はいつも通り、になっていないかということです。
先日小学校を訪問した際に、算数が嫌いだと言う男の子と話しました。なんで算数を学ばないといけないんだろう?という話になったので、好きなものは何?と聞くと、サッカーが好きだと話してくれました。サッカーと算数は関係ないように見えるけれど、実はそうではない。一流のチームは統計データを活用して戦術を立てているので、算数が分からないと戦術は成り立たないんだ、という話をしたら、算数を勉強してみようと言ってくれました。こじつけのように聞こえるかもしれませんが、最初のステップとしてはこういうことが大事なのではないかと思います。一人ひとりに先生がカスタマイズすることはとても大変ですので、そこを担うのはAIではないかと思います。先生とAIの良い組み合わせができれば、「ちょうどの学び」が実現できると思って取り組んでいます。
米田氏:
芦屋市の教育大綱を拝見しましたが、子どもの探究心を育むという話がその通りだと思い、学ぶ内容もそうですが学び方がとても重要だと思いました。学び方に差が出てしまうのは本当にもったいないと思いますので、市長が率先して仰っていただくことでみんなに納得してもらえるととても良いと思います。

- 拡大
- 第3回リフレクション会議
髙島氏:
子どもたちが探究することが重要だと思っていますが、先生たちが探究することはそれ以上に重要です。探究していない大人にいくら探究しなさいと言われても納得感がないですよね。
先生が探究できるような環境を作ろうということで、今年度から始まったのが「ONE STEPpers」という取り組みです。自分も探究したいと手を挙げた先生に対して市で予算を出す取り組みで、外部の講師を招いたり、先進的な事例を見に行ったりする費用を市が出しています。専門家の方とともに、どうやったら授業を変えられるか、探究的な学びを推進できるかを探究しています。探究で得られた成果を探究型の学びの授業として子どもたちに繋いでいくという仕組みです。
濟木:
貴重なお話、ありがとうございました。次に環境面についてお伺いします。芦屋市様は2021年6月に、2050年ゼロカーボンシティ宣言をされたと思いますが、環境計画等も策定され、省エネ・再エネの取り組みを進められていると思います。そちらの取り組みについても教えていただけますでしょうか。
髙島氏:
芦屋市は大きな会社・工場がほとんどありませんので、芦屋市自体が大きな事業者になります。まずは芦屋市自身ができることを率先して取り組むことが大前提だと考え、庁内すべての電気を再生可能エネルギーに変えています。他には、ペーパーレスの取り組みも進めています。私自身が紙文化で育っていないので、例えば市長への説明資料についても印刷して持参ではなく、データで事前に送ってほしいと伝えています。小さな取り組みですが、目に見えるところから始めていこうと考えてのことです。同時に、市民のみなさまのご協力も不可欠です。市民のみなさまの取り組みをサポートしていきたいと、屋根付き太陽光パネルやEVへの補助などの取り組みも加速しています。 芦屋市は、環境に対する意識が高い方が多いので、そういう方々の想いをどう引き出すのかが大事だと思っています。

- 拡大
- 芦屋市地域脱炭素ロードマップ
濟木:
一方的にではなく、地域のみなさまの関心が高いので、それをどうサポートしていくかということを考えて施策を打たれているということですね。非常に理解が深まりました。
今回の対談のきっかけとなったサステナビリティファイナンスについて、鉄道・運輸機構様にお伺いします。発行されている債券は100%グリーンプロジェクトに充当されており、さらにソーシャル性も併せ持つというのが、大きな特徴であると思います。資金調達のお考えについてお聞かせください。
米田氏:
鉄道建設は莫大なお金がかかりますので、国の資金なども入りますが、独立行政法人の資金調達として、財投機関債を発行しています。当機構の名前で債券を発行しており、芦屋市様にもご購入いただいています。
当機構の資金使途についてはどこの路線のどこの線区に充当されたか、チェックを受けています。当機構発行の債券は、国際的な第三者評価機関であるDNVより「サステナビリティファイナンス」の検証を受けるとともに、環境改善効果について厳格な基準を設けるClimate Bonds Initiative(CBI)から、一度の認証で継続的な債券発行が可能となるプログラム認証をアジアで初めて取得しています。グリーンファイナンスやサステナビリティファイナンスといっても、本当にその資金が該当事業に充当されているかが見えないので、色々な投資家様の関心事にもなってきていると認識しています。投資家のみなさまには間接的にはなりますが、環境に配慮した活動に資金を出しているということを思っていただけるというのは大きいと思います。
鉄道・運輸機構が直接的に多くの接点があるのは民間の鉄道事業者、国、地方自治体などで、個人のみなさまに名前が行き届く事業ではありませんが、芦屋市様のように投資表明をしていただけると、市民の方が市のお金がどこでどのように運用されているのか関心を持った際に、グリーンなところに投資しているということで、当機構のことを知っていただけると思っています。資金調達の多様化という面もありますが、ファイナンスを通じて我々の活動をみなさまに知っていただく機会であると思っています。当機構は、全国の全都道府県の事業者様から投資表明を頂いており、これは我々にとって大きなPRにもなると思っています。

- 拡大
- 鉄道・運輸機構のサステナビリティファイナンスの特徴
髙島氏:
おっしゃる通り、トラッキングできるのは良いですね。市民に市のお金を何に使っているのか注目される中で、投資している理由をしっかりと説明できるというのはとてもありがたいです。貴機構のようにグリーン性・ソーシャル性も兼ね備え、社会貢献に資する取り組みをなさっている先に投資すること自体が、社会をよくする第一歩だと考えています。
米田氏:
我々の事業そのものは新幹線を建設しているというもので分かりやすいと思いますが、資金の流れとしてしっかりと説明できるということも重要だと思います。先ほど、金融経済教育のお話もありましたが、「お金がどのように流れるか」知っていただくという意味でも金融リテラシーの向上は大事だと思います。これまで債券発行で調達した資金使途はかつて建設した都市鉄道などの借換えが主なものでした。しかし、今年度は北海道新幹線を建設する資金の一部にも充当されます。多くのみなさまからご投資頂いたサステナビリティファイナンスの資金で北海道新幹線ができるというのはとても意義深いことであると思っています。お金に色をつけない方が効率的なお金の使い方ができるかもしれませんが、敢えて色を付けることで使途を明確にすることも大事であると思っています。
濟木:
鉄道・運輸機構様が発行されている債券は、CBIという取得するのがとても難しい認証を取られています。近年、欧州の投資家を中心に、「ESGファンドと名乗ってはいるものの、本当にESGなのか」という厳しい目が向けられている中で、先行して取り組まれたと思いますが、いかがでしょうか。発行の経緯と併せて、最近の環境面での取り組みなどがあれば、お聞かせください。
米田氏:
サステナビリティファイナンスに関しては、相当早い時期から取り組んできました。最初に発行したのが、2017年に神奈川東部方面線を建設した際で、環境省グリーンボンド発行モデル創出事業第一号となりました。その後、グリーン性のみならずソーシャル性の面も兼ね備えた事業であるということも踏まえて、サステナビリティファイナンスという形で調達しています。
北陸新幹線の延伸においては、敦賀駅の近くに中池見湿地という湿地があり、当初は新幹線が通るルートとなっていました。しかし、この湿地がラムサール条約に登録されたということもあり、ルートを変更するなど、環境への負荷の回避・低減を目的とし「環境管理計画」を策定し、対策を実施しました。こうした対策については、実施後のフォロー・モニタリングも入念に行っており、環境管理計画にも基づき、池に影響がないか虫などの生態系の変化などの調査を行っています。
鉄道・船舶を建設・建造するということ自体が環境にやさしい事業を行っているということで、サステナビリティボンドの認証を受けているわけですが、このようにプロジェクトの過程の中でも環境への配慮を行っています。

- 拡大
- 北陸新幹線開通に伴う環境への配慮(中池見湿地)
濟木:
私も鉄道・運輸機構様のお取り組みを詳細まで知りませんでしたが、サステナビリティファイナンスを通して、みなさまにも理解していただける機会ができるということはとても良いことだと感じました。では、次に、鉄道災害調査隊の取り組みについても詳しく教えてください。
米田氏:
昨年、新たな取り組みとして鉄道災害調査隊を立ち上げました。これまでも当機構が有している技術を活かした災害の復興支援を行ってきましたが、激甚化・頻発化している自然災害に対応するため、新たに鉄道災害調査隊という枠組みを作り、鉄道事業者様から申し出があった際に迅速に動ける体制を作りました。鉄道を速やかに元に戻したいという地域のみなさまの声は強く、最近では年始に被災されましたのと鉄道へも派遣して調査を行いました。
速やかに調査を行うとともに、それぞれにおいて最適な復旧方法を検討する必要があります。また、再び同じような震災が起きた場合への対策を立てる必要もあり、難易度が高い業務だと思いますが、当機構が鉄道建設で培った技術を幅広く生かして貢献する、鉄道災害調査隊のような取り組みについても日本中の色々な方に幅広く知っていただければと思っています。

濟木:
来年1月、阪神淡路大震災からちょうど30年ということで、芦屋市様は30年事業を計画されていると拝見しましたが、こちらについてお話しいただけますでしょうか。
髙島氏:
私は阪神淡路大震災のときは生まれていませんでした。両親や周りの方々からは話は聞きましたが、当時のことは知りません。30年が経ち、芦屋市役所内でも当時を知っている職員は少なくなっています。今後ますます当時を知らない世代が増える中で、当時を経験された方々の話を後世に伝えていくことが重要です。30年事業は、「未来世代」と呼ぶ若い世代がどう記憶を繋ぎ、伝えるかにも焦点を当てています。
現在は、近隣の甲南女子大学の学生と一緒に、芦屋市の広報番組を作るプロジェクトに取り組んでいます。震災を学び、自分たちの言葉で伝える取り組みに力を入れていきます。また、芦屋市では2005年度にあしやフェニックス基金を設立し、芦屋市民だけでなく近畿2府4県の大学の学生等が被災地でボランティア活動等を行う際に助成金を出しています。防災・減災・復興において、芦屋市はお世話になったので、恩返しをするという想いで取り組んでいます。30年を機に、市民のみなさまと一緒に災害に強い芦屋を創っていきたいです。

濟木:
お二方のお話しをお伺い、地域に根差した取り組みを行っているということと、地域の方の声を汲み取って事業を通じた社会貢献をしているということが共通している点であると感じました。
-
 エンゲージメント対談企画「サステナブル・ファイナンスを地域の力に」
(3,045KB)
エンゲージメント対談企画「サステナブル・ファイナンスを地域の力に」
(3,045KB)
資料・画像提供:芦屋市、JRTT 鉄道・運輸機構