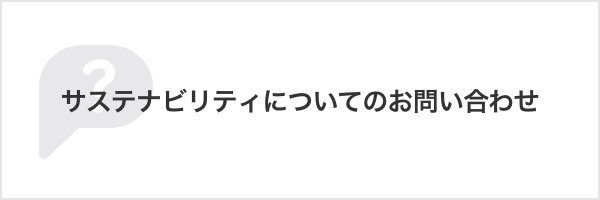削減ペースが加速した政策保有株式
ー政策保有にも求められる「緊張感を孕んだ相互信頼関係」構築ー
西山 賢吾
要約
- 野村資本市場研究所が算出した2023年度の純投資比率は前年度に比べ0.7%上昇して69.2%に、政策保有比率は同0.7%低下して31.2%となった。機関投資家による保有株式量を基準とした議決権行使基準設定が一段と進んだことや、損害保険会社で発生した企業不祥事において政策保有株式の問題が指摘されたことなどが政策保有比率低下の要因と考えられる。
- 政策保有が減少する中で注目されるのは「取引先持株会」と「投資株式の保有目的変更」である。取引先持株会は全体として規模は小さいものの、企業によっては筆頭株主になるなど一定の存在感を有している。取引先持株会の設置目的や意義や取引先持株会を通じた保有の合理性などについて、機関投資家等から説明を求められる機会も今後増えると見込まれる。
- 投資株式の一部の保有目的を「純投資目的以外」から「純投資目的」に変更する事例が散見される。投資家が懸念するのは、保有目的を変更しただけで実態には何ら変化がない「保有株式削減ウォッシュ」である。保有目的を純投資に変更するのであれば、株式運用を行うのに適切な体制の構築や、任意開示も含めた、保有目的が純投資目的以外の投資株式以上に広範で丁寧な情報開示が必要と考える。
- 政策保有株式を巡る環境が厳しさを増す中、さらなる削減と純投資の増加は今後も継続するであろう。一方、政策保有株式についても、保有の合理性の検証や議決権行使など保有先企業を適切にウォッチすることが求められるようになり、「政策保有イコール安定株主」ではなくなりつつある。企業と株主・投資家との新しい関係「緊張感を孕んだ相互信頼関係」の構築は、純投資だけでなく政策保有にも求められてきている。