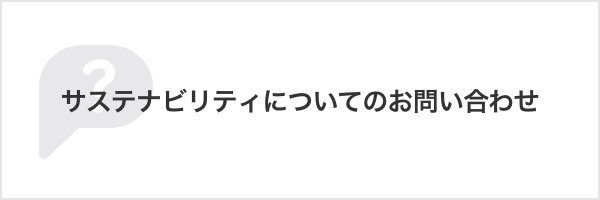コーポレートガバナンス改革「来し方行く末」
-改革に不可欠な「緊張感を孕んだ相互信頼関係」-
西山 賢吾
要約
- 日本における過去20年のコーポレートガバナンス議論のテーマは、「会社はだれのもの」論が盛んであった2005~2008年頃、コンプライアンスが強く意識された2009~2012年頃、成長戦略の中の重要施策とされた2013~2018年頃、そしてサステナビリティ(持続可能性)への関心が広がった2019年~現在と変遷してきた。
- 第二次安倍政権下で成長戦略の柱としてコーポレートガバナンス改革を取り上げてから10年が経過した。この間、一定の成果は見られるものの、国際的に見たROE(自己資本利益率)は依然として低いことや、企業の保有現預金の積み上がりなどの課題が残る。企業の収益性や資本効率性を高め、経済システムに良い「お金の流れ」を作るというコーポレートガバナンス改革の目的達成に向け、さらに歩みを進めることが期待される。
- コーポレートガバナンス改革が進んだことで、株式保有を巡る2つの変化が生じた。一つは、株式保有構造が取引関係の維持、発展を主な保有動機とした政策保有主体から、インカムゲインやキャピタルゲインの獲得を主な保有動機とする純投資家主体へ変化したことである。
- もう一つは、保有先企業の経営に関心を持ち、経営陣による企業価値向上への健全なリスクテイクを後押しすることが株主・投資家の重要な役割と期待されるようになったことである。これらの変化により、改革を一段と進める上では、企業と株主・投資家間で「緊張感を孕んだ相互信頼関係」を基礎とした新しい関係の構築が不可欠といえるであろう。