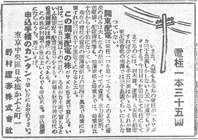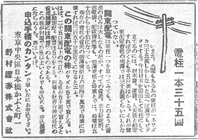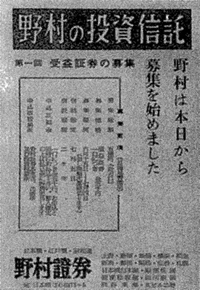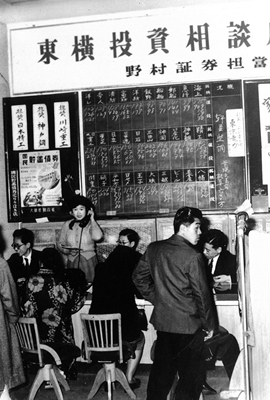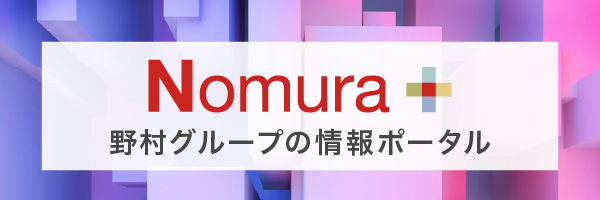サブ-ナビゲーション
-
野村グループについて
- 野村グループ概要
- グループ会社一覧
- シニア・マネージング・ディレクター(執行体制)
- グループCEOメッセージ
-
企業理念 / 行動規範
- 創業の精神
- 行動規範の定着に向けて
-
野村のあゆみ
- 1925年「野村證券」誕生
- 1926年『財界研究』創刊~調査の野村の伝統を承継~
- 1927年ニューヨーク出張所開設
- 1930年日本橋野村ビル竣工
- 1938年株式業務の本格的開始~戦時経済下での投資促進活動~
- 1941年投資信託業務の開始~戦時経済下での投資促進活動~
- 1947年配電株の公募増資~証券民主化を先導~
- 1953年「百万両貯金箱」配布開始~証券貯蓄とけいぞく投資の普及~
- 1955年日本初の実用商用コンピュータ導入
- 1957年野村不動産設立~グループ体制の強化~
- 1967年海外拠点の強化
- 1968年新・従業員持株制度の発足
- 1968年日本初の時価発行増資~時価発行の定着に尽力~
- 1979年「バイ・ジャパン」キャンペーン
- 1980年「中期国債ファンド」開発~公社債ビジネスの積極展開~
- 1987年NTT上場で主幹事/ユーロ債引受ランキング首位~投資家層の拡大~
- 1991年国内営業体制の刷新と管理体制の強化
- 1998年証券総合サービスの取扱開始~規制の緩和~
- 2001年持株会社体制への移行/ニューヨーク証券取引所への上場
- 2007年米インスティネット買収
- 2008年リーマン・ブラザーズ承継発表~グローバル化の加速~
- 2011年復興支援の取組み開始
- 2012年中期経営目標発表~「すべてはお客様のために」~
- 2015年東京2020大会のゴールド証券パートナーに決定~スポーツ支援~
- 創業者「野村徳七」
- 野村グループの歴史
- メディアギャラリー
- 受賞・外部評価一覧
- 文化・スポーツ支援
- サプライヤー取引基本方針
- コーポレート・ガバナンス
- リスク・マネジメント
- コンプライアンス
- 野村のサービス
- サステナビリティ
- 株主・投資家の方(IR)
- ニュース
- 採用情報
- 野村イノベーション
- お問い合わせ
- よくあるご質問
- 野村グループの各種ポリシー